Pianozone開設以前~
クラシック音楽の楽譜をコンピュータに入力して鳴らすことは、PianozoneのWebサイトを開設する前から、個人的に楽しむ形で続けていました。
2000〜2010年代の話ですが、当時のインターネット上には、同じようにクラシック音楽をコンピュータに入力してWebサイトで公開しているサイトがいくつかありました。サーバーの容量制限やインターネット回線の制約から、MIDIデータで公開しているサイトが主流でした。
それらのサイトの音源を聴いているうちに、自分でも少しやってみようかなという気持ちが生まれ、軽い気持ちで始めたのが私の出発点です。
この時点では、自分でデータを入力して鳴らしてみるだけで、特に他の誰かに聴かせることは考えずに制作していました。
そうやってデータを制作するうちに、好奇心から試してみたいことが2つ出てきました。
- 楽譜に書かれた内容以外のテンポやダイナミクスの変化を最小限にして、「楽譜を愚直に読んだだけの演奏」はどんな演奏になるのだろう?
- 無料楽譜サイトや楽譜店の輸入楽譜の棚を見ていると、この世界には現代に至るまで膨大な数の音楽が出版されているが、今現在演奏されている音楽はその中のほんの一部にすぎない。では、今誰も弾いていない音楽は、どんな曲なのだろう?たとえ忘れ去られるのが必然とも言えるようなつまらない音楽だとしても、一度聴いてみたい。
2つ目の疑問については、当時の自分にはお手本の演奏が存在しない音楽を読み解くだけの音楽的な素養がなく、うまくできませんでした。 1つ目の疑問に対する自分なりの回答が、PianozoneのWebサイトにある初期の音源(大まかに2020年ごろまで)になります。
ここ数年のスタイル
しばらく楽譜をそのままデータに変換する形で打ち込みをしていましたが、次第に「このスタイルはもういいかな」と思うようになりました。
このスタイルは音楽を淡々と演奏した音が聴けるし、感傷的な演奏が苦手な自分にとっては悪くない音楽が出てきます。ただ、機械的な演奏として聴いて面白いかというと、正直そうでもない気がしていました。
そんなことを考えると同時に、新しい好奇心が生まれてきました。人間が楽器と向き合って演奏する視点と、コンピュータと向き合ってデータを入力して演奏する視点では、同じ「クラシック音楽」を異なった視点から捉えられるのではないか、ということです。
この時期までに様々な経験を重ね、音楽や音楽以外のものと接する中で、聴いたことのない曲を自分なりに読んで音にしていくだけの土台ができてきたことも、関係しているかもしれません。
こうした経緯から、ここ数年の打ち込みは楽譜をそのまま音にするというよりも、自分なりに楽譜を解釈して、細かいニュアンスにこだわりながら制作するようになりました。楽譜と向き合って音を作っていけそうという感覚も強くなってきたので、お手本になる演奏が聴けない、楽譜は残っているが音が残っていないクラシック音楽を掘り出して打ち込むことも増えました。
ここでいう細かいニュアンスは、「人間が弾いているような音に聴こえるか」という意味ではないことを断っておきます。楽器ではなくコンピューターとその中の仮想楽器と向き合いながら音楽を作っていく時に、その視点から見える「楽譜から少しだけ足したり引いたりした方がいいと感じる、細かいこと」と言えばいいでしょうか。
この文章を書いている時点(2025年10月下旬)では、このようなスタンスで制作しています。初期の打ち込み音源と比べると細かいダイナミクスやテンポの調整があるため、なんとなく聴いただけでも雰囲気は結構違うのではないかと思います。
演奏における制約性と限界の存在について
上の二つの節では、僕自身の打ち込み音楽の変遷について記録として書きました。 以下では、その過程を通して感じたことを、もう少し省察的な視点からまとめておきます。
打ち込み演奏は、超絶技巧のピアノ曲を演奏する時の演奏者の身体の限界や、ピアノという楽器の物理的な限界に対しての一つの回答になる可能性があると思います。
ですが同時に、身体や楽器の「制約」や「限界」からは解放されない、とも思います。
打ち込み音楽を作る時、「楽譜を読んでデータにする自分」が認識能力の限界として存在しますから、入力データを間違えることもありますし、自分の中にある発想しか基本的には道具として使えません。
また、仮想楽器には仮想楽器なりの限界があります。「特定の音域の音だけ不自然」とか「ハーフペダルが実物のグランドピアノほど細かく使えない」など、どの仮想楽器を使うかによって変わりますが、何でも思い通りに動いてくれる仮想楽器は、これまでも、そしておそらくこれからも、存在しないでしょう。
身体と楽器を使う演奏も、データ入力と仮想楽器を使った打ち込み音楽も、不自由さの中で選べるものを選ぶことしかできないこと、そしてその不自由さが時に恩恵となることなど、共通点が多いです。
ですが、両者はまったく異なる視点と姿勢で音楽に向き合っていますし、目標として目指すものもおそらくまったく違う場所になるのではないかと思います。
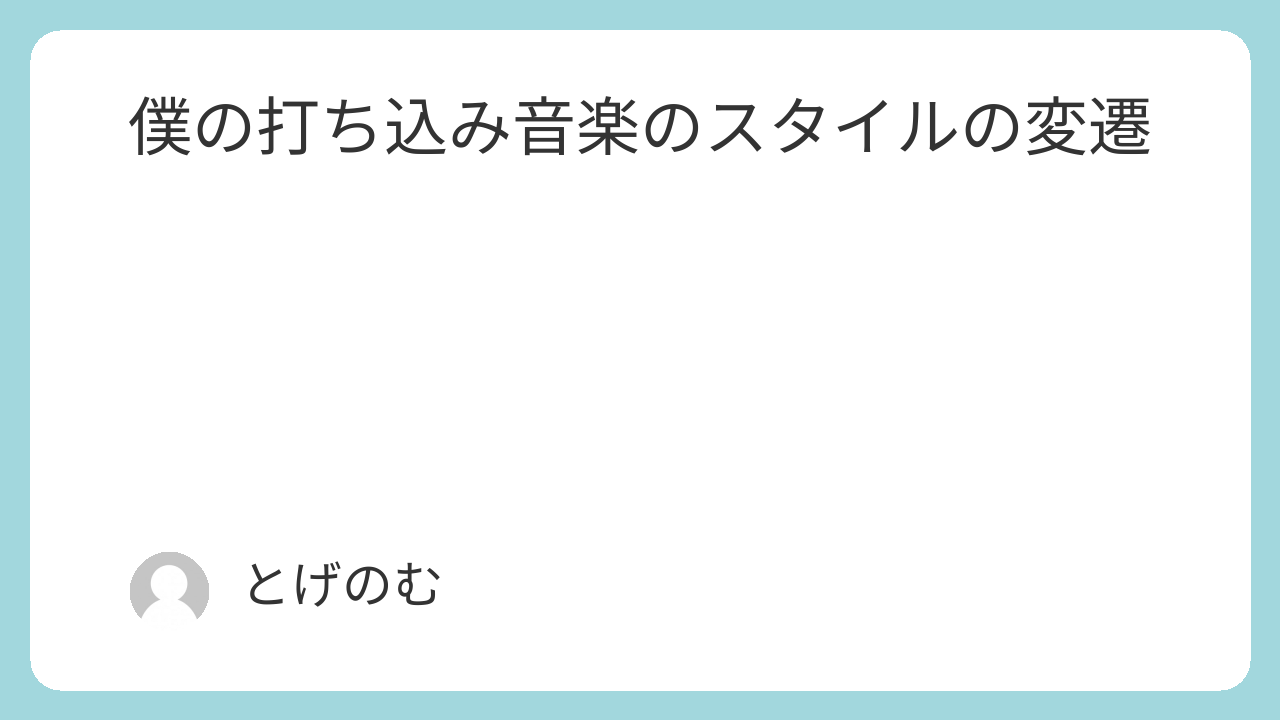
コメント