この記事の後日談になります。
なんか感じる「ビジュアルシンカー」への違和感
しばらくのあいだ、自分は「ビジュアルシンカー」、特に「空間視覚思考タイプ」ではないかという仮説のもとで生活していました。
グランディンの本に載っているテストでは、ビジュアルシンカーっぽい結果が出ましたし、言葉に対して苦手意識もあったからです。
でも、どこかしっくりこない感覚がずっとありました。たとえば、立体迷路や図形の問題が得意というわけでもないし、地図を読むのにも結構苦労します。
気になって調べてみた
違和感の正体が気になって、少しネットで調べてみたところ、岩手大学の川原正広さんによる論文「視覚イメージと言語に関わる認知スタイルの個人差の検討」を見つけました。
この論文では、日本人に合わせた認知スタイルの質問票を作成し、それを実際に使って信頼性を検証した研究がまとめられています。
勘違いしてたかも?
論文には「物体視覚思考」「言語思考」「空間視覚思考」の3つの因子それぞれに関する10項目の設問が掲載されていました。
自己採点にはなりますが、それを自分に当てはめてみたところ
- 言語思考:32点(最も高い)
- 物体視覚思考:18点
- 空間視覚思考:15点
意外だったのは、言語思考が一番高かったことです。これまで自分が「言語が得意」と思ったことはほとんどありませんでした。
でも、「意味が似ている言葉を連想するのが好き」とか「独り言が多い」といった特徴を見ると、思い当たる節はありました。
一方で、空間視覚思考に関係する「図形の回転」や「道順の記憶」には、明確な苦手意識があります。
どうやら、グランディンの本を読んだとき、自分は空間視覚思考の意味を少し誤解していたようです。
思い込みの理由
そもそもなぜ自分を「空間視覚思考タイプ」だと思い込んでいたのか。
考えてみると
- グランディンの著書に掲載されているテストの結果
- 理科が得意、機械に興味があるといったイメージ
- そして何より、「言語が苦手」という自覚
こういった要素が重なって、自分をそっち側に分類したくなっていたのかもしれません。
おわりに
今回の話は、グランディンのテストも川原さんの論文に載っていた質問票も、あくまで主観に基づいたものです。
なので、この記事も科学的な分析ではなく、ただの「個人的な感想」に過ぎません。
自分がビジュアルシンカーなのか、言語思考タイプなのか。正直、それ自体はそこまで重要なことではないと思います。
でも、人の趣味嗜好が多様であるように、思考のスタイルにもいろんなパターンがあるということには、とても興味を惹かれます。
自分の思考のクセを少しでも言葉にしてみると、それだけで新しい視点が見えてくる気がします。

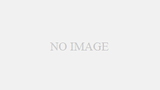
コメント